概要
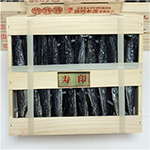 身欠きニシン(みがきニシン)とは、ニシンの干物のことである。水揚げされた鰊は、生の状態では、日持ちがしない。冷蔵技術が発達していない時代は、内臓や頭を取り除いて乾燥させるのが一番合理的な保存法だった。大量の鰊を日本各地に流通させるため、干物に加工したものが身欠き鰊である。
身欠きニシン(みがきニシン)とは、ニシンの干物のことである。水揚げされた鰊は、生の状態では、日持ちがしない。冷蔵技術が発達していない時代は、内臓や頭を取り除いて乾燥させるのが一番合理的な保存法だった。大量の鰊を日本各地に流通させるため、干物に加工したものが身欠き鰊である。
すでに享保2年(1717年)の『松前蝦夷記』に、ニシンの加工品として「丸干鯡」(ニシンを内臓も取らずそのまま干し上げたもの)、「数の子」、「白子」などと共に「鯡身欠」が記載されている。
名称由来
「身欠き」とは、戻した干物が筋ごとに取れやすくなることからついた俗称で、「磨きにしん」という表記は誤りである。また、脂の少ないものが上物とされ「上干」という。
歴史
かつて北日本、特に北海道の日本海沿岸では、春になれば海が白子(精子)で海岸が白く染まるほどニシンが押し寄せ、漁獲されて浜に数尺の高さに敷き詰められたニシンの上を、人が往来するほどだった。
江戸時代からニシン漁で各地の漁村が栄え、ニシンで財をなした各地の網元の「鰊御殿」と呼ばれる豪邸が、今も当時の栄華を伝える。水揚げされたニシンは番屋などで干物や鰊粕に加工され、内地に流通(北前船を参照)させることで、蝦夷地開拓の資金源の大きな助けとなった。一方、内地に渡来した身欠き鰊は、保存に便利なタンパク源として各地に流通した。言海はニシンの干物を「貧人の食とす」と記し、当時は安価で貧困層の食物だったが、後に漁獲高の減少からニシンが値上がりしたため、現在は高級食材となりつつある。京都では身欠き鰊の煮物がおばんざいの定番となっているほか、日本各地で身欠き鰊の煮物や鰊漬けが伝統料理となっている。
製造方法
明治大正時代のニシン漁場では、ニシンをさばいて加工する作業を「鰊潰し」と呼んだ。
まず、水揚げしたニシンをロウカと呼ばれる板倉に収蔵する。数日間たてば魚肉が軟化し、カズノコが固まって加工しやすくなるので、テックビ(指袋)をはめた手でえらを開いて腹を裂き、内臓とカズノコ、白子を抜き取る。内臓を抜き取ったニシンがある程度溜まれば、藁で22,3匹ずつ結束する。このように縄でまとめた鰊の束を「連」と呼び、50か51連で「1本」と呼ぶ。2人がかりで処理するニシンの量は、1日で8本(約9千匹)が目安とされた。ちなみにニシン漁場では、私娼を「七連」(ななつら)と呼んだ。彼女たちは身欠きニシン7連分の金額で買えるからである。
縄に繋いだニシンを2日ほど納屋に干し、サバサキリと呼ばれる薄刃の包丁で尾から頭に向けて開き、さらに2週間ほど乾燥させて完成させる。100本を樹皮で結わえたものを1束とし、24束を1梱にして秋田県、山形県、新潟県など東北、北陸方面に出荷する。ニシン潰しの際に出たカズノコは干し上げたのち食品として出荷し、白子や笹目は北陸方面に肥料として出荷する。
ニシン干場の土壌には大量のニシン油が滲み込んでいるため、漁期が済んだ春以降は畑として利用された。
現在ではよく洗ったニシンを機械干しし、加工しやすい程度に水分が落ちた時点で三枚におろし、再度送風による機械干しにする。1週間程度乾燥させたところで、頭などを落とし成形し、1ヶ月程度倉庫で熟成させる。ニシンは脂分が多い魚で、内部までゆっくり乾燥させないと腐ってしまうため技術が要求された。寒風が吹く北国に向いた特産物である。
利用
一般的に魚の干物は焼いて食されるが、身欠きニシンは米の研ぎ汁に1週間ほど漬けて戻した後、煮物や甘露煮などに加工して食べることが多い。柔らかく煮含めた身欠き鰊を具としたにしんそばは京都や北海道西部の名物となっている。
一方、北海道や東北地方では酒の肴として、鰊の半生干しに味噌を付けそのまま食する食べ方もある、鰊を野菜と共に付け込んだ鰊漬けは北日本の越冬の貴重な食糧であり、鰊を昆布で巻いて煮含めた鰊の昆布巻きは日本各地で広く食べられている。
出典:ウィキペディア





